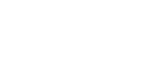特集 ドキドキ
舞台の魔法
たとえば、男が女になる。たとえば、女が男になる。
たとえば、若者が年寄りになる。たとえば、現代人が未来人になる。
舞台の上で、ドラマの中で、さまざまな演者が、
鮮やかな「変身という魔法」を見せてくれる。
華やかな「変身という魔法」で魅せてくれる。
しかし、それは、魔法などという簡単なものではなく、
演者の一生における努力の結晶であり、
変身しても変わることのない強い意志であることをあなたは知るだろう。
いのうえひでのり劇団☆新感線主宰/演出家
昔も今もやっていることは変わらない。
舞台の面白さは、現実を忘れられること。
Photo / Ko Hosokawa Text / Rie Shintani
今やなかなかチケットが取れない活劇集団として圧倒的人気を誇る「劇団☆新感線」。彼らの舞台を映画館で観る新しい鑑賞スタイルの「ゲキ×シネ」も10周年を迎え、ますますファンを増やしている。その新感線の旗揚げメンバーであり、主宰・作家・演出家として34年間にわたり劇団を支えている、いのうえひでのりさん。「最初は、こんなにも長く続くとは思っていなかった」という背景には、彼と演劇と人との意外で素敵な出会いがあった。
「もともと映画が好きだったんです。中学2年のときにブルース・リーの映画に出会って、はまって、映画館に通いました。新感線のベースでもあるチャンバラは、間違いなくブルース・リーがきっかけです。その後は、千葉真一さんの空手アクション映画を観るようになって。なかでも当時映画館で観て、ものすごい衝撃的だったのが『直撃地獄拳 大逆転』。この映画からも大きく影響を受けています。誰が観るんだろうっていうくらい注目度の低かったへんてこりんな映画なんですけど、僕にとってはすごく面白くて。後で知ったんですが、新感線の座付き作家の中島かずきも同じ時期にその映画を観ていたんです。僕は福岡で、彼は筑豊で。なんか、つながっていたんですね」
そして2人は高校時代に出会う。演劇の大会で勝ち進んでいたいのうえさんの舞台の面白さに感動した中島さんは、その劇をモチーフにオリジナル脚本を執筆。それをいのうえさんに送ったことで、交流がはじまった。
「かれこれもう三十数年の付き合いですね。でも、そもそも僕が演劇の道に進んだのは仕方なかったというか。自主映画を作りたかったのに高校に映画研究部がなくて、似ているからまあいいかと思って選んだのが演劇部(笑)。高校時代はコンサートみたいな大音量で好きなロックをかけられるような劇をやっていました。新感線でも『五右衛門ロック』のような歌楽曲を多数とり入れたRシリーズがあるので、そう考えると、昔も今もやっていることはあまり変わらないのかもしれないですね」
卒業後は大阪芸術大学芸術学部舞台芸術学科に進み、つかこうへい作品『熱海殺人事件』にて「劇団☆新感線」を旗揚げ。ずっと交流のあった中島さんは、1985年から劇団に参加している。このまま芝居で食べていけたらいいなぁと、漠然と将来を夢みているうちに「あっという間に50代です」と、笑う。
好きこそものの上手なれ。演劇が好きであることはもちろん、ドキドキさせてくれる何かがあるからこそ、続けたくなるのだろう。演出家としては、最初に脚本を読むとき、舞台の初日を迎えるときに毎回ドキドキを味わうそうだが、一番のドキドキは、やはり舞台そのもののなかに──。
「舞台の面白さは、現実じゃない世界、異空間や異次元に連れていってくれることなんです。芝居を見ている時間だけは別の世界に入っていける、現実を忘れられる。それが楽しさであり、たまらなくドキドキするんですよね」
そう語るいのうえさんの瞳は、きっと中学時代と変わらない輝きを放っている。
SANZUIの著作権は、特に明記したものを除き、すべて公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
実演家著作隣接権センターに帰属します。
営利、非営利を問わず、許可なく複製、ダウンロード、転載等二次使用することを禁止します。