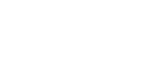生成AIについて○○さんに聞いてみた ―Google編 YouTube鬼頭武也さん―
法制広報部 穎川一仁
生成AIを巡っては、誤った情報の拡散や個人情報の漏えいのほか、著作権侵害やクリエイターの仕事が奪われるのではないかといった懸念が示され、著作権法や不正競争防止法、肖像権、パブリシティ権などとの関係について議論が行われている。
その一方、創作活動の補助や、新たな手法として期待されるところもある。
この企画では、様々な立場の方に考えを伺い、私たちは生成AIとどう向き合っていけばよいのか考えていきたい。
第2回は、世界を代表するIT企業であるGoogleのYouTube/日本音楽パートナーシップ ディレクターの鬼頭武也さんに、同社が開発する音楽関連の生成AIや、開発にあたってのポリシー、生成AIを巡る懸念に対する取り組みなど、お話を伺った。
(取材日:2025年6月4日)
Googleが開発・提供する生成AIサービス(特に音楽関係)について教えてください。
Google全体では、あまりにも多くのAI関係のサービスがあるので、YouTubeに関係するものを中心にお話したいと思います。
YouTubeでも様々な部分でAIの導入を進めており、例えばYouTube ショートの背景を生成する「Dream Screen」や、自動翻訳・吹替機能など、生成AIを活用した新機能の提供を進めています。これらを活用することでクリエイターは、動画制作の強力なサポートを得ることができます。
音楽関連のAIについては、クリエイターやアーティスト、業界関係者とも話し合いを進めながら、二つの切り口でサービス開発を進めているところです。
一つは、プロフェッショナルなアーティスト、音楽プロデューサー、音楽クリエイターの創作の支援ツールで、「Music AI Sandbox」と呼んでいます。
例えば、色々なキーワードをプロンプトとして入力して楽曲を生成することもできれば、元の曲をこういうふうにアレンジしてみてという対話型での生成もできるような機能を実験しています。まだすべてのアーティストが自由に使える段階ではなく、「AI インキュベーター」プログラムとして、世界中の様々なジャンル、様々なキャリアステージのアーティスト、プロデューサーなど、私たちからお声がけをしてテスト中の機能を使っていただいています。その中で、フィードバックをいただいて、またツールに反映してという過程を繰り返しています。
アーティスト、実演家、音楽プロデューサーと、それぞれ観点も異なると思いますし、国によっても考え方が違ったりもします。ですので、幅広い様々な方々に本プログラムに参加いただいて、それぞれの観点からのフィードバックをいただきながら、最適なプロダクトのあり方を模索しています。
音楽の創造性を支援する、言い換えると壁打ち相手になるような音楽の生成支援プロダクトを作りたいと考えています。皆様と一緒にツールを作っていくというアプローチで、責任を持って丁寧に進めています。
二つ目は、ショート動画用に独自の音楽を生成するための試験運用版のツール「Style Transfer」です。協力を依頼した少数のアーティストの楽曲のスタイルを変えることができます。
これによって、アーティスト、クリエイター、ファンのいずれにとってもメリットのある、活気あるエコシステムが育まれると考えています。現在はアメリカのみで実験的に展開しています。
AIサービスを開発する上で、YouTubeとして特に意識していることはありますか?
2023年8月に、YouTube史上初となる、AIを音楽に活用するための基本的な考え方として、「AI Music Principles」(以下、「音楽AIの基本的な考え方」)を制定しました。
ここでは、「①YouTubeは音楽業界としっかりと連携して、責任ある改革の追求と、クリエイティビティの強化を目指すこと」、「②YouTubeはYouTubeのクリエイティブコンテンツを保護する強固な実績を継続させていくこと」、「③これまで構築してきた信頼性と安全性に取り組む組織と構築してきたコンテンツポリシーを、さらに拡張していくこと」が示されています。
生成AIは、既存の著作物をトレーニングさせる、活用するという要素なしに技術開発はできません。YouTubeでは、基本的に、生成AIの学習元となる著作物に関しては、権利者に然るべきコントローラビリティを技術的に提供していくという考え方を明確にしています。これには、3つの要素があります。
1点目は、アトリビューション(帰属)の明確化です。基になった著作物の権利者、何を使ったのかを正確に表示することで、見ている人が分かるようにするということです。
2点目は、自分の著作物が使われるのか、使われないのかというコントロールを、権利者に提供すること。
3点目は、収益化で、自分の著作物が使われた場合には、合理的な考え方に基づいて権利者が対価を得られるような仕組みを用意すること。
この3点が製品開発においては重要だという考え方を明確にして、社内でも合意をし、社会へ提示しています。生成AIコンテンツは、視聴する方にとってもリスクが絡みうるものです。YouTubeというプラットフォームは、安心して見聞きできる 生成AIコンテンツがあがっている状態を作りだすという宣言でもあります。
前述の「AIインキュベーター」プログラムは、正にこの原則を実践するもので、YouTubeでは、世界中で本プログラムを展開して、アーティストやレコード会社、音楽関連のビジネスを展開する事業者などと密に連携を取りながら、音楽関連AIサービスの開発を進めています。日本では、バーチャルシンガー・ソフトウエア「初音ミク」などの開発で知られる、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社などの協力を得ています。
このようにYouTubeではクリエイターとの連携を非常に重視しており、多くのフィードバックを得ながら、音楽のクリエイティビティを広げてくれるAIサービスの導入を目指しています。YouTubeとしては、生成AIを活用した新機能の導入により、クリエイターの創作活動を一層支援することはもちろん、ファンからの、二次創作を含めたリアクションが活発になることも期待しています。
これまでも、テクノロジーは様々な形で音楽のあり方を変えてきました。新しいテクノロジーが生まれたことによって、音楽を作れなかった人、音楽をやりたくてもできなかった人が、できるようになっていったという背景はあると思います。潜在的に素晴らしい才能を持っているクリエイター、アーティストにも、AIによって可能性を提供できればと考えています。
「音楽AIの基本的な考え方」
1) AIの存在を無視することはできません。YouTubeは音楽業界と協働し、AIを責任を持って活用していきます。生成AIが、クリエイティビティの新しい扉を開く中、この急速に進歩する分野において、YouTubeと音楽業界は、これまでの長期的な協働関係を継続し、責任を持ってAIを活用していきます。音楽業界と連携して、責任ある改革の追求と、クリエイティビティの強化を目指します。
2) AIがクリエイティビティの新時代への扉を開く一方で、適切な権利保護と、音楽業界への機会提供がなければなりません。YouTubeはYouTube上のクリエイティブコンテンツを保護する強固な実績を継続させていきます。著作権者の利益とYouTubeのクリエイターコミュニティの利益とのバランスをとるために、長年にわたって非常に多くの投資を行っています。
3) YouTubeは、業界をリードする信頼性と安全性に取り組む組織とコンテンツポリシーを構築してきましたが、AIの課題に対応するため、さらにそれらを拡張していきます。YouTubeは、YouTubeコミュニティを保護するためのポリシーや、Trust & Safety チームに長年投資してきましたが、これらはAIで生成されたコンテンツにも適用されています。生成AIには、商標や著作権の悪用、誤情報やスパムといった現在既に存在している課題をさらに増やす可能性があります。しかし一方で、AIはそういった問題のあるコンテンツの識別に利用することもできます。YouTubeは視聴者、クリエイター、アーティスト、作詞・作曲家のコミュニティを安全に保護するためのAIを活用した技術、すなわち、Content ID、違反コンテンツを検知してポリシーを適用するシステムに引き続き投資し、今後この取り組みをさらに拡大していきます。
YouTube Official Blogより引用
https://blog.youtube/intl/ja-jp/news-and-events/2023_08_youtubeai/
生成AIに対する実演家からの懸念については、どのように考えていますか?
YouTubeが提供する音楽関連のAIサービスについては、前述の通り、そもそも実演家の皆様が懸念を抱くものにならないよう、クリエイターと密に連携しながら開発を進めています。これに加えて、YouTubeとして大きく3つのアプローチによって、安心して生成AIの技術をユーザーの皆様が利用できる環境整備に取り組んでいます。
第一に、コミュニティガイドラインによる対応です。YouTubeのコミュニティガイドラインは、コミュニティを安全に保つために作成されています。このガイドラインでは、YouTubeで許可されること、禁止されることが定められており、AIで生成されたコンテンツを含むYouTubeプラットフォーム上のあらゆる種類のコンテンツ(動画、コメント、リンク、サムネイルなど)に適用されます。更に、コンテンツが改変または合成されている場合は、視聴者にそれを知らせるようにするアップデートも行いました。実物のように見えるコンテンツについては、改変または合成されたメディア(生成AIを使用したものを含む)で作成したコンテンツであることを視聴者に開示を求めます。一貫してこの情報を開示しないクリエイターに対する措置も検討します。例えば、AIによって生成された現実味のあるコンテンツをアップロードする際には「生成AIを利用していること」の情報表示義務や、なりすまし、人権を侵害するような行為の禁止などが定められています。
第二に、前述のコミュニティガイドラインをはじめとしたYouTubeが定めるルールに違反する動画について、YouTube側でAIと人間の組み合わせで検出し、適宜削除します。人間の目による判断が必要なケースも多いので、業務的に大きな負荷がかかる部分ではありますが、安心して使っていただけるプラットフォームであるために重要なものですので、力をいれて取り組んでいます。公開された動画のチェックだけでなく、アップロード時(公開前)の削除も含みます。また、個人情報の保護の一環として、プライバシーガイドラインに基づき、"AI生成コンテンツやその他の合成コンテンツがあなたの容姿や声に似ている場合"の申告窓口も設けています。
最後に、技術的な対応です。AIなどの最先端技術も活用して、より迅速で的確にルールに違反するコンテンツを検出するシステムの開発に取り組んでいます。まだ実用化には至っていませんが、コンテンツIDのような技術の延長線上で、AIで生成されたコンテンツや、AIで模倣された音声や顔などの画像・動画などを検知して、「これはAIで生成されたものである」ことをYouTube側で判断し、ユーザーに対して表示するような仕組みを開発中です。この技術が完成すれば、フェイクはフェイクであることが明示されるようになるので、少なくとも視聴者の誤認は機械的に防げるようになるのではないかと思います。
YouTubeとしては、生成AIは既存の創造に取って代わるものではなく、創造のプラスになるものであるべきと考えています。これらの総合的な取り組みは、まさに音楽 AI の基本的な考え方を実践するものであり、実演家の方々の懸念の払拭にもつながるものと考えています。
国内においては、生成AIに関する法的な規制を強めるべきという意見がある一方で、生成AIが国境を越えて開発・提供されている実態に鑑みれば、国内法の改正だけでは十分な成果が見込めないのではないかといった意見もあります。生成AIがクリエイターの創作活動を害さず、適切に利用されるにはどのような対策が必要であると思いますか?
生成AIが適切に利用される社会を実現する上では、複合的な対応が重要になると考えます。具体的には、YouTubeとしては、アウトプットの場でのコントロールが重要だと考えています。AIで作られたもの全てがフェイクであるとも限らず、やはり一番の問題は、ゼロから作ったものと、AIで作ったものが、同じ土俵で区別なく表示されてしまうことだろうと思います。だからこそ、YouTubeは前述の3つのアプローチによって、安心・安全に使っていただけるプラットフォームであり続けられるように、AIに対する責任ある取り組みを継続してきます。
より前向きなAIの活用という観点で、"YouTubeならでは"の実現を模索しています。それが、プロフェッショナルなクリエイターの創作の活性化だったり、ファンやリスナーによる創作だったり、YouTubeがあるからこそ生まれる新しい文化のうねりを作り出していきたいと思います。そのための様々な環境、ツールを整えていくことで、生成AIの力でYouTubeらしい文化貢献ができるのではないかと考えています。生成AIでクリエイティビティの新しい扉を開くべく、クリエイターの皆様と連携しながら、歩みを進めて行きたいと思います。
――お話を伺って、YouTubeが実演家を含め、クリエイターと連携しながら生成AIを活用しようとする明確な姿勢を感じました。「AIに対する責任ある取り組み」がどのような成果をもたらすのか、芸団協CPRAとしても、引き続き注視していきたいと思います。本日はありがとうございました。
生成AIについて○○さんに聞いてみた シリーズ
≫【第1回】ボカロP編 ねじ式さん