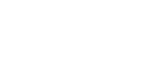生成AIについて○○さんに聞いてみた ―ボカロP編 ねじ式さん―
法制広報部 穎川一仁
生成AIを巡っては、誤った情報の拡散や個人情報の漏えいのほか、著作権侵害やクリエイターの仕事が奪われるのではないかといった懸念が示され、著作権法や不正競争防止法、肖像権、パブリシティ権などとの関係について議論が行われている。
その一方、創作活動の補助や、新たな手法として期待されるところもある。
この企画では、様々な立場の方に考えを伺い、私たちは生成AIとどう向き合っていけばよいのか考えていきたい。
第1回は、ボカロPとして、数多くの楽曲制作を行うねじ式さんに、音楽活動から著作権・著作隣接権についての意識、そして生成AIに対する考えなど、お話を伺った。
(取材日:2025年5月19日)
いつから音楽活動を始められたのですか?
中学生の時です。バンドを組んで作詞・作曲をしながら、楽器はエレキギターを担当していました。
MTR(マルチトラック・レコーダー)やオールインワン・シンセサイザーを購入して、デモテープの制作もしていたんですよね。MTRでギターを打ち込んでみたらミャーミャーした音になって、ギターは実際に弾いた方がいいなとか、当時からいろいろやっていて。バンドメンバーにデモを聞かせて、こんな感じで演奏するよって曲のイメージを伝えるのが結構楽しかったんです。自分でプリプロダクションするのが好きだったんですね。
今考えると、この経験が後々ボカロPとして、全部一人で演奏することに繋がっているのかなと思います。
ボーカロイドで楽曲制作を始めたきっかけは何でしょうか?
バンドでメジャー・デビューもしたのですが、結局解散してしまって。その後もバンドを新たに結成しては、また解散を繰り返して、バンドでやる音楽はやり切ってしまった感覚がありました。
これからどうしようかと考えていたときに、友人からボーカロイドの存在を教えてもらったんです。年齢、性別、本名も非公開で、ボーカロイドのキャラクターに良い曲を書くことができれば、純粋に認められるという新しいシーンを知りました。
友人に誘われてコスプレイヤーが集まる大型イベントに行ったときに、たまたま初音ミクを見て、ボーカロイドが新しいカルチャーの中心にいるんだなと感じたことにも背中を押されたように思います。打ち込みもやるし、いろんな楽器が弾けるんだからボカロPをやってみたら、とアドバイスももらって。
やっぱり曲はどうしても書き続けたいという気持ちが強くあったので、「ボカロPになれば、自分の創作の幅を楽しく広げることができるし、多くの人に自分の楽曲を聴いてもらえるきっかけになるのではないか」と感じて挑戦することにしました。
そしてボカロPになると思い立って、2013年8月に「ねじ式」という名前でニコニコ動画のアカウントを作って、ボーカロイドというカテゴリーに自分の曲を投稿し始めました。
ボカロPとして活動する中でこだわっていることを教えてください。
僕は楽曲制作においては、作詞、作曲、編曲、楽器演奏から打ち込み、ミックス、マスタリングといった一連の作業を極力自分で行うようにしています。
もちろん大変なところもあって、音楽仲間からは「一部でも外注すればいいのに」と言われることもありますが、それはやっぱりこだわりですよね。システマティックにやってしまうと、曲の強さがなくなってしまう、自分でやるからこそ伝えられる魅力があると信じています。
ボカロPというのは、本来オールインワンでやるものだと思っているので、新幹線で移動中にポチポチ打ち込んだり、楽しみながらも苦労してこだわって作っています。
それから、楽曲のプロモーションも自分で行っています。雑誌やラジオ、テレビの影響力は昔とは変化してきていますよね。今は、SNSやホームページを使って、どういうふうに情報を見せるべきか、深く考えて戦略を立てていかないといけません。
例えば、土日は、食事に行ったり、映画やお芝居を観に行ったりする人も多いので、投稿しても再生率の初動が上がりにくいです。
アナリティクスを活用して、YouTubeのトラフィックが集中しやすい金曜日の夜8時頃に投稿するとか、いろんな人に視聴してもらえる適切なタイミングで自分の曲を投稿するようにしています。
この10年でもトレンドが変わってきているので、常に対策を練りながらプロモーションも含めて取り組んでいます。
プロモーションまでご自身でやられているとは驚きです。
音楽が大ヒットすると言ったら、90年代から2000年代前半は、広告代理店が仕掛けたり、テレビや映画の主題歌で知られて、CDが購入されるという流れがほとんどでした。しかし、今はSNSの「いいね!」とか、バズることがカギになってきています。
また、サブスクリプション型音楽配信サービスでのリスナーの再生回数によって、レコメンドが上がってきます。
楽曲のクオリティが重要なのは当然ですが、今の音楽業界で生計を立てていくためには、こういうことを意識しながら、自分で戦略を立てて、こまめに軌道修正していくことが重要だと思っています。
ボカロPをやっていて良かったと思った出来事や、活動するなかで印象的だった出来事があれば教えてください。
僕が制作した楽曲が、たくさんの人に聞いてもらえた、気に入ってもらえたと感じる時がとても嬉しいです。ボカロPとして発表した曲がヒットしたんですが、その後に人気のVTuberが「歌ってみた」で素敵なアレンジをしたものを投稿したことで、さらに大きくヒットしたこともありました。自分の楽曲の新たな一面を知れますし、作品への愛が伝わってきて、やっていて良かったという気持ちでいっぱいになりますね。
サブスク全盛期の今、CDは売れない時代と言われますが、僕は毎年1000枚ほどCDを作っています。
音楽を聴くことが手軽になった今でも、台北、ソウルなど現地のイベントに参加して、直接対面でCD販売もしていますが、「いつもサブスクで聴いている音楽を作っているあなたから、直接CDを買うという『体験』を買っているんだ。それがエキサイティングなんだ」なんて言われたこともありました。とても嬉しかったですし、黄金時代に比べて規模は縮小したとはいえ、フィジカルを直接買ったり、手にするということはなくならないんじゃないかなという考えは、僕の中ではあります。
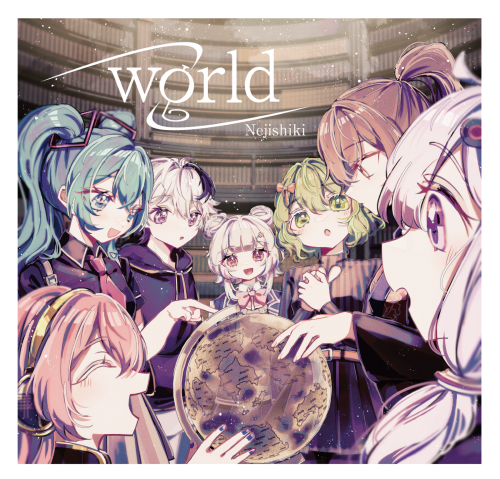 12枚目のアルバム「world」
12枚目のアルバム「world」ボーカロイドも一つのジャンルとして認識されてきた、そんな気もします。ボカロP出身の人気アーティストも多いですよね。
ボカロPから出てきたYOASOBIのAyaseさんとか、米津玄師さんらもそうですけれども、それは別にボーカロイドを武器にしてきたというよりも、自分をどう売り出して、自分をどう世の中に伝えるか、もっと言うとアニメのコンテンツにも真摯に向き合って、自分が持っているスキルや感性でどんなふうに相乗効果を与えられるのか。
要するに自分を、メタ的な目線というか、客観視できるクリエイターというのは、ボカロ以降すごく増えたと思うんですよね。
従来のように、音楽や活動の方向性を事務所などに委ねてしまうようなやり方ではなくて、仕事も自分で考えて選んでいると思います。僕も、いろんな案件をいただく時に、こういう曲だったら協力できるかな、といろいろ考えます。ビジネスと音楽をバランスよく考えられるクリエイターがかなり増えてきたと感じます。
ねじ式さんは、自身の楽曲に関する権利や実演に関する権利を、JASRAC、NexTone、CPRAに任せていらっしゃいますが、権利について意識するようになったきっ かけがあったのでしょうか?
最初にバンドでデビューしたときは、正直レコード会社に任せきりで、権利には意識がいっていませんでした。
でも、ボカロPとして個人で音楽活動を始めると、いろいろな方から楽曲の利用に関する問い合わせをいただくようになりました。そして、こういうニーズにしっかり対応する必要があるという意識が芽生えると同時に、個人で対応することの限界を感じました。
そんな中で、動画投稿サイトの運営会社から、著作権や著作隣接権の管理について丁寧に教えてもらう機会があったんです。自分が得られる収入が何に基づくものなのか、明細の見方がわかり為になりました。これが権利を預けようと考えるきっかけになりました。
任せることで管理の手間が大幅に省けたのはもちろん、個人管理では対応しきれないような利用まで管理してもらえることが、ありがたいなと思っています。知れば知るほど、今の時代に権利管理団体にお任せしないで対価を得る未来があんまり見えなくて。むしろ自分の手が届かないところまでちゃんと徴収してくれるし、自分の作品が「住所不定」じゃない状態にあることが大事な時代だと思ったんですね。
少し生々しい話にはなりますが、アーティストとして生計を立てる上で、こういった著作権や著作隣接権を管理する団体から受け取る分配金は大きいです。コロナ禍でライブや即売会イベントが軒並み中止になり、活動が停滞してしまって、経済的に苦しかったときにも、収入が得られる仕組みがあることは本当に助かりました。
しかし、ネット上の変な情報に惑わされて、実際の制度や仕組みを理解しないまま、対価を得るチャンスを逃して、音楽で生計を立てるのが難しいという理由で業界を去ってしまう人をたくさん見てきました。
だから、音楽仲間には、事あるごとに権利の管理を任せることがいかに重要かを力説しています。著作権等を管理する団体に権利を預けることで、自分の作品を利用してもらう機会を増やし、しっかり対価を受け取る選択肢もあることを知ってほしいなと思います。
生成AIをめぐっては、実演の無断利用や創作活動の場が奪われるのではないかとの懸念がある一方、創作活動の補助や、新たな創作の手法として期待する声も聞こえてきます。クリエイターとして、生成AIについてどのように捉えていますか?今後、音楽文化にどのような影響が生じてくると思いますか?
精神論になってしまいますが、僕自身は、楽曲制作においてクリエイティブな作業だと思うところを生成AIに任せることはないと思います。
創作活動は、自分の心を潤すものでもあってほしいし、自分の中で素敵な楽曲を書けたと実感できることが僕の中ではとても大切なので、それを生成AIに任せるのは違うと思っています。
おそらく、楽曲制作を単なるビジネスだと捉えている人は、クリエイティブな作業であろうと、生成AIを活用して効率化することに肯定的だろうと思います。良い悪いはさておき、ビジネスに使える楽曲ができれば、それで目的は達成されるからです。
これからは、AIによって生成された楽曲と、そうでない楽曲が混在していくことになると思います。でも、人が創作する楽曲が淘汰されていくのかというと、そうはならないと思います。
なぜなら、楽曲の制作された背景や、クリエイターへの想いも含めて、「音楽を楽しむ」ファンが相当数いるからです。イベントでわざわざ僕の楽曲が収録されたCDを買いに来てくれるファンは正にそれです。こういったファンには、AIによって生成された楽
曲が良い曲だったとしても、心に刺さらないのではないでしょうか。例えるならば、安くて美味しいお寿司が食べられるチェーン店ができたからといって、大将が丁寧に握ってくれる高級な寿司屋の需要はなくならない、といった感じですかね。
ねじ式さんは、著作者であると同時に、実演家の立場でもありますが、生成AIの捉え方に違いはありますか?
ありますね。実演家が最もアンフェアな立場に置かれていると感じます。
そもそも、生成AIが登場する前から、高品質なソフトウェア音源などの登場により、実演家は演奏機会の減少に直面してきました。
例えば、DAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)でソフトウェア音源を使用して打ち込んだドラムの音が、近年はかなりリアルになったので、生のドラムのレコーディングが減ったといった感じです。
また、一般的に著作者に比べて、楽曲の売り上げから得る印税も非常に少ないので、
実演で生計を立てるのは本当に大変なのが実情です。
すでにそんな状況下にあるのに、生成AIでさらに追い打ちをかけられるとなれば、実にアンフェアではないでしょうか。
例えば、生成AIが、ある音源のギターの演奏を学習した場合に、その演奏にウォーターマーク(透かし)が入って、自分の演奏が学習されたことが分かり、収入が得られるような仕組みが考えられれば、もう少しフェアになっていくのではないかと思います。
――お話を伺って、実演家が安心して活動が続けられるよう、対応を考えていく必要性を強く感じました。芸団協CPRAとしても、引き続き議論を深めていきたいと思います。本日はありがとうございました。
ねじ式さんプロフィール

2013年8月6日に「六等星の夜」を投稿しボカロPデビュー。作詞・作曲だけでなく、全ての楽器演奏も自ら行っているマルチプレイヤー。卓越したポップセンスから生み出されるギター・ピアノを中心としたメロディラインと、そこに乗せる強さと繊細さを兼ね備えた歌詞は、聴くものに対して時に力強く先導する強さを、時に寄り添うような優しさを見せる。活動開始から12年の間に制作したオリジナルアルバムは12枚、参加したコンピレーションアルバムは10作品以上、YouTubeをはじめとした動画再生サイトの総再生数は約2700万回を超えている。
オフィシャルサイト https://www.nejishiki.com/
YouTube https://www.youtube.com/@nejishiki
X https://x.com/nejishiki0221
FaceBook https://www.facebook.com/nejishiki/
Instagram https://www.instagram.com/nejishiki0221/