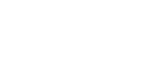ロングインタビュー 田中 泯
Text / Yuma Ochi Photo / Ko Hosokawa
盆踊りが原点。
無名であることに踊りは宿る。
現在、映画、テレビに俳優としても出演し、独特の存在感によって見る者を魅了し続けている舞踊家・田中泯。1970年代以降、裸体の前衛ダンサーとして芸術の中心地であるパリ、ニューヨークをはじめ、東欧諸国から東南アジアに至るまで数多くの都市・地域で踊り、常にセンセーションを巻き起こしてきた。初舞台から半世紀余り。踊り続けるうちに世界の舞台芸術界にその名を轟かせる稀代の舞踊家となった今も、山梨で農業を営みながら究極の踊りを探求し続けている。
スポーツの世界から芸術の世界へ
―泯さんは元々バスケットボールの国体レベルの選手だったと伺いました。踊りを本格的に始めたのはいつ頃からでしょうか?
田中 中学から高校、大学までバスケットボールをやっていました。もちろん上を望んでいましたが、しかし、大学に入って上には上がいると気がついたんです。アスリートの世界の競い合いに嫌気が差してしまい、オリンピックの前に辞めてしまいました。それでバレエのスタジオに見学に行ったんです。理由は簡単で、幼少期に盆踊りに出会って以来、大好きだった踊りを正式に習うにはどうしたらいいかと考えたからなんです。
―初舞台はいつだったのでしょうか?
田中 オリンピックに関連して芸術祭が開かれていて、その枠内で『マダム・バタフライ(蝶々夫人)』のバレエ版が公演されたんです。そこで、蝶々夫人の結婚シーンの参列者でちょっと出れば済むような役をもらいました。端役と言っても、ダンサーでなくては駄目なわけだよね。僕はまだ習い始めでしたが、一応、つま先を伸ばして、ピッピッとやるぐらいはできたんです。
―この初舞台が、舞踊を仕事とするきっかけになったのでしょうか。
田中 ならなかったですね。なんか違うと思っていました。むしろ転機となったのは、1968年に観た土方巽の『肉体の叛乱』ですね。それと大学では殆ど授業に出席しませんでしたが、籍を置いていた東京教育大学(現筑波大学)の舞踊学研究室に時々顔を出し、歌舞伎研究者の郡司正勝さんや舞踊評論家の市川雅さんらの知己を得て話している内に、踊りの技術とは何なのか、技術があればそれは踊りになるのかなどと考えるようになりました。踊りをやり続けようと思ったのは、それを突き止めたいと思ったからなんです。
芸能と芸術の間で
―幼少期に踊りの魅力を知るきっかけになったという盆踊りの体験もその志向に影響しているのでしょうか。
田中 はい。子どもの頃に自分が好きになった盆踊りや神楽のような芸能としての踊りと、当時習っていた芸術としての踊りとの違いは何か、そんなことを常に考えていました。それは言わば土の上の踊りと、観客が入場料を払って観る舞台という場所での踊りです。その違いはすごく大きいと思っていました。一般の人たちこそが、実は年がら年中、郷里の踊りを見ているわけです。日本は、まさに芸能の宝庫ですから。芸能の間口は本当に広い。家の中でテレビを観て子どもが踊り出すことがあります。そういう世俗的な踊りすべてを含めて考えていないと、踊りの本質には到達できない。自分は前衛の芸術舞踊をやっているなんて言ってられないですよ。僕はそのことを20代の初めから予感していました。
―70年代以降、既存の芸術の枠を破るダンスを次々と発表されますよね。泯さんは裸体の舞踊家とも呼ばれて、パリやニューヨークでもセンセーションを引き起こしましたね。
田中 劇場では踊らず、野外でほぼ裸体で踊っていました。客席を疑い、音楽を疑い、舞台を疑い、既存のダンス公演の形態のすべてを疑っていました。だから野外で踊ったし、衣裳も疑っていたから、必然的に裸体に辿り着きました。普通ダンスは、基本的には身体を動かしていくわけですよね。僕の場合は、動くのではなくて動けない状態、例えばブリッジのような姿勢を選んで数時間その姿勢に留まるんです。それは普通に踊るよりもかなり苦しい体勢ですが、僕の身体は感覚で充満していて、音、空気、ほこりだとか観客の視線など、そういうものが身体に押し寄せてくるのがわかるんです。
―泯さんが踊る時、泯さんの身体に満ちている感覚が観客にも伝播していると感じる瞬間があると思います。
田中 実は、踊りは違いを見せることではなくて、みんなに共通のものをその現場で探すことなんです。そして見つかった何かがその場に居合わせた人たちの中に届くかどうかが問題です。届けば、その人の身体は変わりますよね。「あっ」と思う瞬間がある。そこから初めて踊りという境地に僕たちは到達できるんです。こちらが準備したものを観客の前で踊るだけでは本当は片手落ちなんです。
自然の中の暮らしと踊り
―泯さんは現在、山梨県で農業を営んでいらっしゃいます。東京を離れて農業を始めた理由は何でしょうか?
田中 僕自身は、子どもの時からずっと自然に親しんできましたから、僕にとって自然は神様みたいなもので、ずっと身体の中では生きていたんですね。ただ、暮らしの仕方がそんなに自然に近いものではなかった。それで40歳の時に、もう一度自然の中に戻る必要を感じました。言葉が生まれる以前に人類が過ごした長い時間や踊りの起源を知りたくて農業を始めたんです。農業は生物の歴史に関わる仕事ですから。
―農業をやることで身体の感覚や考えは変わったでしょうか?
田中 農業をやっていると気象に鋭敏になります。僕たちはどこに行っても自分が中心だけども、気象というのは簡単に中心が変わる。あるいは中心がふっとなくなることが起こる。それと同じような風に人間は振る舞わなければならないのではないかと思ったんです。というのは、人の社会には常に上下関係があったり、優劣があったりする。でも、小さな頃は、人と同じ方が嬉しかったんじゃないかと思うんですね。それが次第に勝ち負けが大きな喜びになっていく。そうした社会の構造へのある種の批判的なモデルを探す機会でもありました。
踊ること/ 演じること
―2002年以来、映画やドラマで俳優としてのお仕事も多数こなされています。踊ることと演じることの間に何か違いはあるでしょうか?
田中 演じることというのは、一つの役の人生に入り込んでいく。あるいはその人生が身体に入り込んでくるということだと思います。踊りというのは、自分の身体から感覚やエネルギーを全部放出して、反応を返してくる観客一人ひとりと自分が繋がるか、切れるかを覚悟しながら行う作業なんです。最初から一切、観客を一つにまとめようと思わない。踊りは、観客一人ひとりが絶対的な個の時間の中にいられることを保証する関係の中にあるんです。
―泯さんが役者として出演される時「存在感がある」とよく言われますが、仰られたように、通常の役者の有り様と異なる方法で存在しているからかもしれませんね。
田中 見た人が「存在感」という言葉で表すものが何なのかは、むしろ、僕の方が知りたいぐらい。でも実際僕は、存在することに賭けてきた。第一そうでなければ、簡単に観客から捨てられていきます。バレエだって同じように踊っているけど、観客は「あの子がいいね」と言うじゃないですか。それも、存在感だと思う。それは技術を越えたところにあると思います。
究極の踊りを求めて
―70歳になる現在まですでに果敢に踊りを探求されてきたかと思いますが、これから挑戦したいと思われることはありますか?
田中 ダンスは特定のダンサーや振付家に留まるものではなく、途方もなく長い歴史の中で引き継がれ、人類の誰もが持ちうるものだと思うようになりました。ひょっとしたら空気とかそういうものと同じように目に見えない物質として存在するんじゃないかと思うんです。だから、有名性という問題に、今ダンスをやっている人は目覚める必要があると思います。有名人であれば興行は成功するかもしれません。しかし、本来、名前が踊りを助けてくれるはずがないんです。無名な身体にこそ、踊りは宿るのではないか。例えば、ある人が個性を持って踊るとするじゃないですか。でも、それはものすごく小さな単位の踊りで、その人の所有物にしかならないんじゃないかなという気がするんです。そうしたダンスは、経済の論理だとか、世の中の体制の中に取り込まれ、有名な踊り手としてその人の名が残るかもしれないけど、人類のダンスの本流からは外れます。でも、もしそうした体制をひっくり返し、無名の人によって繋がれてきた踊りの歴史の一部になることができるとすれば、僕はそのための生贄になりたい。そして、それが人類への贈与になるとしたら、ダンサー冥利に尽きますね。
SANZUIの著作権は、特に明記したものを除き、すべて公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
実演家著作隣接権センターに帰属します。
営利、非営利を問わず、許可なく複製、ダウンロード、転載等二次使用することを禁止します。