vol.011「世界のクラシックシーンで活躍」
一昨年来、クラシック音楽に関して最もテレビをにぎわした話題といえば「のだめカンタービレ」。お陰でクラシックの演奏会の入りが随分よくなったと聞く。その主役は「のだめ」こと野田恵だが、もう一人の主役はピアノ、ヴァイオリンの名手にして、指揮者を目指している千秋真一先輩。ドラマの役柄だから実際の指揮者の姿とは違うのだが、玉木宏が演じている千秋は実にかっこいい。つまり、指揮者の仕事の中のかっこいい部分がデフォルメされているといっていいだろう。だが、玉木宏は当然指揮者ではなく、指揮の勉強をしたわけでもない。かっこよく役柄を演じるためには指南役がいる。その指南役が今回インタビューする飯森範親さんだ。飯森さんもまたかっこいい指揮者だ。そのかっこよさは演じるためのかっこよさではなくて、音楽を表現するために磨き上げられた充実しきった内面から醸し出されるかっこよさだ。世界中のオーケストラから招かれて指揮をしているというキャリアがそれを証明している。テレビ映りも格別だ。毎年お正月に放映されるNHKの「ニューイヤーオペラコンサート」の指揮を2年連続で務めたので、テレビの画面に大きく映し出された彼の指揮する姿をご覧になった方も大勢いるのではないかと思う。世界のクラシックシーンで活躍する飯森範親さんに、音楽との出会いからあまり知られていない「指揮者の裏側」までを、社団法人日本演奏連盟事務局長でCPRA広報委員の菊地一男委員が伺った。
(2008年03月18日公開)

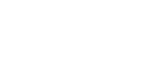



 ―― そもそも、音楽の道へ進むきっかけはどういうことだったのですか。 父方の祖父が京都大学時代に朝比奈隆先生と一緒にカルテットを組んで、アマチュアで演奏をしていたんです。朝比奈先生がバイオリンで、祖父はチェロ。その辺から自然とクラシックの環境が生まれたんでしょうね。まず4歳のときからピアノを習わせてくれました。それと、親戚にいずみたくがいて、父と仲が良かったんです。で、父も音楽が好きでかなり詳しかったんですよ。父からクラシックのレコードを聞かされるのと、祖父が枕もとでチェロを弾くという環境で育ったんです。ただ、祖父も父も逆に音楽家の事情を知っていたんで、僕が音楽家になりたいと言ったときには大反対されました。母だけは、好きなことはやらせてあげたらと言ってくれて。
―― そもそも、音楽の道へ進むきっかけはどういうことだったのですか。 父方の祖父が京都大学時代に朝比奈隆先生と一緒にカルテットを組んで、アマチュアで演奏をしていたんです。朝比奈先生がバイオリンで、祖父はチェロ。その辺から自然とクラシックの環境が生まれたんでしょうね。まず4歳のときからピアノを習わせてくれました。それと、親戚にいずみたくがいて、父と仲が良かったんです。で、父も音楽が好きでかなり詳しかったんですよ。父からクラシックのレコードを聞かされるのと、祖父が枕もとでチェロを弾くという環境で育ったんです。ただ、祖父も父も逆に音楽家の事情を知っていたんで、僕が音楽家になりたいと言ったときには大反対されました。母だけは、好きなことはやらせてあげたらと言ってくれて。 ―― 帰国されてからはさらに広がって。 初演の際の大阪フィルでの演奏が大好評で、NHKホールの開館20周年記念で東京上演させていただき、その時は東京交響楽団が演奏。すると、東響が創立50周年にむけて指揮者を探してる時期で、東響の皆さんも僕のことを気に入ってくださったようで専属指揮者にさせていただいたわけです。それがなければドイツのマネージャーの話もなかっただろうし、ヴュルテンベルク・フィルハーモニーの音楽総監督の話もなかったと思うんです。もしかしたら、吉村七重さんの一本の電話がなかったら、今の自分はなかったかもしれませんね。
―― 帰国されてからはさらに広がって。 初演の際の大阪フィルでの演奏が大好評で、NHKホールの開館20周年記念で東京上演させていただき、その時は東京交響楽団が演奏。すると、東響が創立50周年にむけて指揮者を探してる時期で、東響の皆さんも僕のことを気に入ってくださったようで専属指揮者にさせていただいたわけです。それがなければドイツのマネージャーの話もなかっただろうし、ヴュルテンベルク・フィルハーモニーの音楽総監督の話もなかったと思うんです。もしかしたら、吉村七重さんの一本の電話がなかったら、今の自分はなかったかもしれませんね。 ―― 指揮者は、ふだんどういう練習をしてるんですか。 とにかく楽譜を丹念に読むことですね。たとえば、8分の5拍子というのがあれば、それを2と3にわけるか3と2にわけるか。1、2、1、2、3でいくのか、1、2、3、1、2でいくのかで、曲の感じが全然違ってしまいます。勿論、そういうことはスコアリーディングのほんの一部のことですが、スコアを読みながら手を動かしたり、どういう振り方が音楽的に良いのか考えているんです。オーケストラのテンポ感、音色感、そして音の強さやバランスなどを頭のなかでイメージすることが「覚える」ということなんです。頭の中でイメージをつくっていくわけですね。
―― 指揮者は、ふだんどういう練習をしてるんですか。 とにかく楽譜を丹念に読むことですね。たとえば、8分の5拍子というのがあれば、それを2と3にわけるか3と2にわけるか。1、2、1、2、3でいくのか、1、2、3、1、2でいくのかで、曲の感じが全然違ってしまいます。勿論、そういうことはスコアリーディングのほんの一部のことですが、スコアを読みながら手を動かしたり、どういう振り方が音楽的に良いのか考えているんです。オーケストラのテンポ感、音色感、そして音の強さやバランスなどを頭のなかでイメージすることが「覚える」ということなんです。頭の中でイメージをつくっていくわけですね。 ―― 最近は人気者になって、テレビに出る機会も多いですね。NHKのイヤーイヤーオペラコンサートも2年続けてやられたし、「食菜浪漫」など、料理番組にも出演されていますよね。料理はご自分でも? けっこうやりますね。昨年とか一昨年は僕の人生において一番忙しい年で、精神的にも肉体的にも大変な中で、唯一息抜きができるのが料理だったかなって思っています。母が料理やケーキ教室の先生をしていたので、僕もその手伝いを見様見真似でやってて、自然と身についたんでしょうね。勿論、食べるのも大好きですから(笑)。
―― 最近は人気者になって、テレビに出る機会も多いですね。NHKのイヤーイヤーオペラコンサートも2年続けてやられたし、「食菜浪漫」など、料理番組にも出演されていますよね。料理はご自分でも? けっこうやりますね。昨年とか一昨年は僕の人生において一番忙しい年で、精神的にも肉体的にも大変な中で、唯一息抜きができるのが料理だったかなって思っています。母が料理やケーキ教室の先生をしていたので、僕もその手伝いを見様見真似でやってて、自然と身についたんでしょうね。勿論、食べるのも大好きですから(笑)。