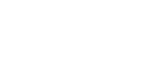パブリシティ権の保護を巡る韓国の動向
張 睿暎(CHANG,Yeyoung)(獨協大学教授)
日本では、芸能人等の氏名、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利であるパブリシティ権は、最高裁判決において認められた権利だが、法律による明文規定は存在しない。
他方、韓国では、BTSなど韓流スターの世界的人気が高まる中で、裁判例が積み重ねられたほか、不正競争防止法が改正され、芸能人等の氏名や肖像等を無断で使用した商品の製造・販売行為に対し、差止や損害賠償請求などができることが明確になった。しかも、現在、国会に提出されている著作権法改正法案ではパブリシティ権の創設も提案されている。
芸能人等の氏名・肖像の保護を巡る韓国の積極的な動きについて、張睿暎・獨協大学教授に紹介いただいた。
1. パブリシティ権に関する従来の裁判例
「パブリシティ権(right of publicity)」が韓国の裁判所にて初めて言及されたのは、1995年の「イ・フィソ事件(ソウル中央地方法院1995.6.23.宣告94カ合9230判決)」においてである。
この事件で裁判所は、「パブリシティ権とは、財産的価値のある有名人の氏名や肖像等のプライバシーに属する事項を商業的に利用する権利」であると述べ、パブリシティ権の存在を認定した。
それ以降、多数の下級審判決でパブリシティ権が肯定されてきた(ソウル高等法院2000.2.2.宣告99ナ26339判決、ソウル中央地方法院2005.9.27.宣告2004ガ単235324判決、ソウル中央地方法院2004.12.10.宣告2004ガ合16025判決、ソウル中央地方法院2006.4.19.宣告2005ガ合80450判決等)。
2006年には、肖像権に関する事案の大法院判決(大法院2006.10.13.宣告2004ダ16280判決)で、「何人も、自身の顔その他社会通念上特定の個人を識別できる身体的特徴に関して、みだりに撮影もしくは描写されず、公表されず、営利目的で利用されない権利を有し、このような肖像権は憲法第10条第1文により憲法的に保障される権利である」とし、人格権の一種である肖像権には、「顔を営利目的で利用されない権利」が含まれるとした。
無断で利用された場合には、不法行為による損害賠償(慰謝料)が認められるが、顔を営利目的で「利用する権利」があるとはしていないことから、使用料に相当する損害賠償やその他の損害賠償が可能であるか、権利の譲渡・相続が可能であるかについては議論があった。
下級審判決も判断が分かれていた。
例えば、財産権としてのパブリシティ権は、法律、条約などの成文法や確立された慣習法のいずれにも根拠がなく、必要性があるという理由だけで、物権と類似の独占排他的な財産権であるパブリシティ権を認定することは難しいとして、パブリシティ権を否定する判決(水原地方法院2014.1.22.宣告2013ガ合201390判決)もあり、パブリシティ権の成立要件、譲渡の可否、相続性、保護対象、存続期間、侵害の場合の救済手段等を具体的に規定する法律的根拠が設けられて初めてパブリシティ権が認定されうると判示している。
大陸法系である韓国の法体系における整合性の観点から、人格的要素と強く結合している肖像等に関する権利を、財産権であるパブリシティ権として新たに設定することは、民事法全体の体系に照らして慎重に検討すべきであるという指摘もあった。
また、既存の不法行為に基づいては差止請求できないことも理由に、より強い(英米法のような)パブリシティ権を立法しようとする議論が続いた※1。
2. 不正競争防止法改正とBTS大法院判決
そんな中、他人の成果物の不正使用に関する旧不正競争防止法の一般条項(当時のカ目※2、現行法上のパ目)が立法され、その後のBTS事件大法院判決(大法院2020.3.26.宣告2019マ6525判決)で、芸能人の写真を大量に収録した雑誌等を販売した行為が不正競争防止法第2条第1号カ目(当時)の成果物盗用行為に該当すると判断され話題になった。
K-PopグループBTS(防弾少年団)の所属事務所である債権者が、芸能人らの写真や記事等を主な内容とする雑誌を製作・販売する債務者を相手取って、BTSメンバーの写真を大量に収録した付録及びフォトカード等を製作して販売する行為が、不正競争防止法第2条第1号カ目の成果物盗用行為に該当すると主張して、本件特別付録等の製作・販売の差止等を求めた事案であった。
原審は、債務者が本件特別付録を製作・販売する行為は、公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自己の営業のために債権者の成果等を無断で使用する行為に該当するとして、本件仮処分決定を一部認めた。
大法院は、以下のように判断し、原審の判断を支持した。
「債権者は本件専属契約により、BTSの音楽・公演・放送出演等を企画し、音源や映像等のコンテンツを製作・流通させるなど、BTSの活動に相当な投資と努力を投じた。それによりBTSに関連して築かれた名声・信用・顧客吸引力が相当な水準に達したところ、これは『相当な投資や努力により作られた成果等』であると評価でき、だれでも自由に利用できる公共の領域に属するものであるとはいえないため、他人がこれを無断で使用すれば、債権者の経済的利益を侵害することになる。芸能人の氏名や写真等を商品や広告等に使用するためには、芸能人やその所属事務所に許諾を受けるか一定の対価を支払うのがエンターテイメント産業分野の商取引慣行であることに照らしてみると、通常の情報提供の範囲を超え、特定芸能人に対する特集記事や写真を大量に収録した別冊やDVD等を製作しながら、芸能人や所属事務所の許諾を受けず、その対価を支払わなければ、商取引慣行や公正な取引秩序に反するとみることができる。債務者が発売した本件特別付録は債権者が発行する写真集との関係でも需要者が一部重複し、上記写真集の需要を代替する可能性が十分あるため、債権者との関係で競争関係を認めることができる。よって債務者が本件特別付録を製作・販売する行為は公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自己の営業のために債権者の成果等を無断で使用する行為に該当する。」
本判決は、旧不正競争防止法第2条第1号カ目(現行パ目)の判断基準を大法院レベルで初めて提示し、無断で芸能人の写真等を大量に使用した行為がカ目の不正競争行為に該当すると判断したものである。
本判決で大法院は、明示的に「パブリシティ権」という言葉は使っていない。しかし、BTSの専属契約書には、グループ名称、写真、肖像等に対する権利を「パブリシティ権」とし、所属事務所に帰属させる条項があった。第一審判決は、この契約書を根拠に、いわゆる「パブリシティ権」と呼ばれる「成果」が所属事務所に帰属することを認めていた。
本大法院判決で、人の氏名・肖像の財産的価値が保護されうることは明確になったものの、パブリシティ権が積極的な「権利」として保護されるのか、譲渡や相続ができるのかについては明らかになっていない状況であった。
しかし、裁判所が不正競争防止法を通じて芸能人の肖像等を保護したことが注目され、その後、不正競争防止法が再度改正され、パブリシティ権を間接的に保護する新たな規定が導入されるきっかけとなった。
3. 不正競争防止法の再改正とパブリシティ権の間接保護
2021年12月7日、不正競争防止法が法律第18548号として再度改正され、2022年6月7日から施行される。新法は、一般条項である既存の第2条第1号カ目をパ目へ移動し、データの不正利用に関するカ目およびパブリシティの不正利用に関するタ目を新設した。
タ目は、「国内に広く認識され、経済的価値を有する他人の氏名、肖像、音声、署名等、その他個人を識別できる表示を、公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で、自身の営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為」を不正競争行為と規定する。
新設の理由として、
ⅰ)韓流の影響力が拡大し、有名人の肖像や氏名等を使用する製品やサービスが多様化するにつれ、違法商品の製造・販売行為も増加しているものの、有名人の財産的損失や消費者の被害を適切に保護するには限界があったこと、
ⅱ)パブリシティ権を独自の権利として保護するとしても、その一身専属的な性質から譲渡や相続はできないところ、有名人の氏名や肖像に関する商標権は譲渡や相続できることから、既存の商標権との間で問題が生じる可能性があることなどが挙げられた。権利付与よりは行為規制のほうがパブリシティの保護に適切であることを意味すると思われる。
また、ⅲ)上記BTS判決で大法院は、有名人の肖像や氏名等の有する経済的価値が「相当な投資と努力の成果」に該当するとして、これを無断使用した行為を不正競争行為として規制したが、あくまでも不正競争防止法の補完的な一般条項に基づいた判決であり、今後発生しうる多様な形態の無断使用行為を適切に規制するには限界があることが挙げられた。
そこで、有名人の肖像や氏名等の人的識別表示を無断使用する行為を不正競争行為の一類型として明確に規定することで、健全な取引秩序を確立し、不当な被害から消費者を保護することを改正理由としている。
新たなタ目は、上記BTS判決の文言をそのまま反映したものであるといえる。
すなわち、「国内に広く認識され、経済的価値を有する他人の氏名、肖像、音声、署名等その他個人を識別できる表示」が、パ目(旧カ目)の「その他、他人の相当な投資や努力で作られた成果等」に該当すると宣言したことになる。
「国内に広く認識され」という要件が設けられているので、広く認識されていない人の場合は、一般条項であるパ目や民法750条(不法行為)による請求が可能であるが、侵害の認定や認定時の損害賠償額に違いが出ることになる。
また、遺族による請求等も難しいと思われる。ここでいう「他人」が「生存者」を意味すると思われるからである。関連法である商標法第34条第1項第6号は、「著名な他人の氏名・名称または商号・肖像・署名・印章・雅号・芸名・筆名またはこれらの略称を含む商標」は登録できないとしているが、大法院はここでいう「他人」は「生存者」を意味するとしている(大法院1998.2.13.宣告97フ938判決)。そのため、改正法によるとしても、人格主体の死亡後に遺族等による不正競争行為の主張は認められないと思われる。
4. 著作権法全部改正案におけるパブリシティ権保護の試み
肖像等財産権(パブリシティ権)を明記した著作権法全部改正案(議案番号2107440)が2021年1月15日に発議され、現在国会小委員で審議中である。しかし、同時期の2021年2月2日に発議された上記不正競争防止法改正案(議案番号2107846)が先に成立し、パブリシティの不正利用行為は不正競争防止法により先に手当されることになった。
ただ、不正競争防止法による保護には限界もある。不正な競争行為が発生した場合に、消極的に他人のパブリシティの無断利用行為を差し止めることができるのみで、本規定を根拠として、積極的にパブリシティ権を主張することはできない。個人の氏名や肖像等が有する顧客吸引力が必ずしも努力の成果でない場合もあり、パブリシティ権が果たして投資や努力を理由に保護されるべきものであるかという根本的な疑問もある。
現在の規定だと、他人のパブリシティを無断利用する者が競争関係にいない場合は、不正競争防止法を適用することは難しい。パブリシティ権を不正競争防止法により間接的に保護することに対しては、「公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法」であるか否かで侵害が判断されることへの違和感もある。「健全な取引秩序を維持することを目的」とする不正競争防止法によるパブリシティの保護は、どうしても競業者の存在と営業上の利益の侵害を求めることになり、著作者や実演家などクリエイター個人の(人格的側面も踏まえた)権利保護とはいえない部分がある。
その点、現在国会で審議中である著作権法全部改正案は、肖像等の保護に関する新たな章を新設し、クリエイターの権利保護を図る。
まず、案第2条第22号で、「『肖像等』とは、人の氏名・肖像・声またはその他これに類似するもので、その人を特定できるものをいう」と「肖像等」の定義を新たに規定する。
そして、「肖像等の保護」と題する案第5章を新設し、案第123条(保護を受ける肖像等)、案第124条(著作権等との関係)、案第125条(他の法律との関係)、案第126条(肖像等財産権)、案第127条(肖像等財産権の制限)、案第128条(肖像等財産権の一身専属生)、案第129条(肖像等財産権の行使等)を設けている。案第126条により、「肖像等が特定する個人は、自身の肖像等を商業的目的のために一般公衆に広く認識されるようにする方法で利用する権利を有する」ことになる。
国内の裁判所は、パブリシティに関する事案において、民法や不正競争防止法など異なる法律を適用して保護したり、あるいは反対に保護を否定するなど、その立場が明確に確立されてこなかった。
そうした中、パブリシティ権を著作権法に権利として明確に規定しようとするところに、本著作権法全部改正案の意義がある。肖像等財産権により、肖像等の主体は、他人にそれを利用許諾することができるようになる。肖像等財産権を一身専属的な権利とみて、譲渡を否定しているため、独占的利用許諾を受けたとしても、例えば芸能人の所属事務所の権利行使には一定の限界があると思われる。
外国人の肖像等財産権の認定は相互主義によるとする。肖像等は写真や映像など著作物に収まった形で利用される場合が多いことを考慮し、肖像等財産権の行使が著作物の利用を不当に制約しないように、公正利用(フェアユース)など著作権制限規定を多数準用する。侵害判断の基準は明記せず、著作権制限規定等を準用するため、侵害判断は結局裁判所に委ねられることになると思われる。
本改正案は長らく国会で審議中であり、その間、他の著作権法改正案も複数発議されているため、審議過程においてさらに規定が変わる可能性もある。本著作権全部改正案における「肖像等財産権」規定がどのような形で成立するか、今後が注目されるところである。
また、本改正案が成立すれば、「特許法、実用新案法、デザイン保護法、商標法、農水産物品質管理法、著作権法または個人情報保護法に、第2条から第6条まで、および第18条第3項と異なる規定があれば、その法律に従う」と規定する不正競争防止法第15条第1項により、不正競争防止法の新たなタ目の適用は制限されることになると思われる。
※1 韓国におけるパブリシティ権の過去の立法の試みの概要については、以下を参照されたい。
張 睿暎「パブリシティ権、もしくは『人格表示権』?」(早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP)2015年 6月コラム)https://rclip.jp/column_j/20150629-2/ (2022年4月15日最終訪問) (▲戻る)
※2 「目」とは、韓国の法体系において「条」「項」「号」に続くもので、日本法の「イロハ・・・」に該当する。韓国法では「ガ、ナ、ダ、ラ、マ、バ、サ、ア、ジャ、チャ、カ、タ、パ、ハ」の順でつけていく。 (▲戻る)